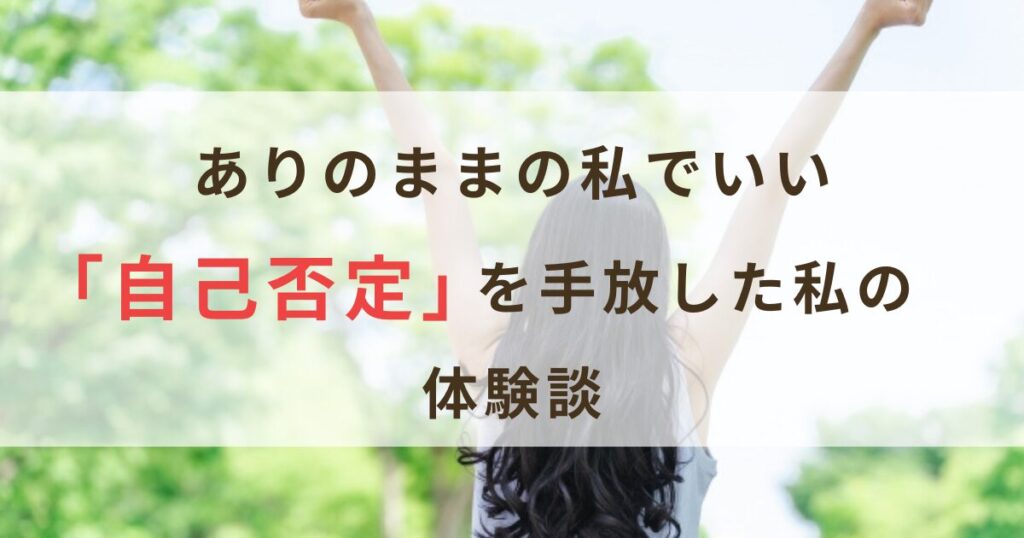
はじめまして。
自己理解と自己受容の専門家として活動をしている
心理カウンセラーの松田 真由(まゆ)です。
「どうして自分を好きになれないんだろう」
「他人の気持ちばかり気にして、本当の自分がわからない」
「頑張ってるのに、いつも空回りしてしまう」
そんなふうに感じたことはありませんか?
私も長い間、そう感じながら生きてきました。
「こんな自分じゃダメ」と思いながら、自分にダメ出しばかりして、他人の目や気持ちばかりを気にして、心がどんどん苦しくなっていったのです。
でも、今では、「そのままの私でも大丈夫」と思えるようになってきています。
この記事では、私が自己否定から抜け出し、自己受容によってラクに生きられるようになるまでの体験談をお話しします。
もしあなたが今、生きづらさや自己否定の中にいるのなら、きっと何かヒントが見つかるはずです。
幼少期編:相手の気持ちばかり考えて育った私

私は和歌山県ののどかな田舎の町で、二人姉妹の長女として生まれ育ちました。
物心がついた頃から内向的で人見知り。
よく会う親戚の人でも、慣れるまでには母の後ろに隠れるほどでした。
父は家事や育児に関わるということはあまりなく、会話はいつも母とばかり。
なので、幼い頃から母にべったりでした。
そんな私は家では「うちにお金はない」という言葉をよく聞いていたため、子どもの頃から“我慢すること”が当たり前になっていました。
「何か欲しい」と感じても、それを口にすることはあまりなく、
どちらかというと、「これなら買ってもらえるかもしれない」と、母が買ってくれそうなものを選ぶクセがついていたのです。
母の機嫌をうかがい、「いい子でいなきゃ」「迷惑をかけちゃいけない」と自分に言い聞かせていた私。
そうして、知らず知らずのうちに、本当の気持ちを表に出すことをやめてしまっていました。
そのため小学校5年生の頃、みんなのように「自分の意見」を持てなくて、“何を思っているのか自分でわからない。私って変なのかも…”と不安になったのを覚えています。
じつは、自分の意見を表に出さないことで、家族はもちろんですが友人関係でも、波風を立てずに相手との関係性を保とうと私はしていたのです。
思春期編:誰にも言えなかった痛みと孤独

小学生の頃はクラス替えもなく、同じ友人たちと安定した関係の中で過ごしていました。
けれど、中学生になると環境が大きく変わり、私は初めて“自分の苦手なこと”を思い知ることになったのです。
友達づくりへの苦手意識と、唯一の親友に依存していた私
中学生になると、小学校の頃の人間関係とは大きく変わり、私は一気に「人見知り」を発動してしまいました。
それまで1クラスしかなかった環境が、6クラスに増えたことで、クラスの大半が“知らない人たち”になってしまったのです。
みんながどんどん仲良くなる中、私はどこかで「うまくやらなきゃ」と思いつつも、自分からは話しかけられず、心細さばかりを感じていました。
そんな私にとって、唯一の救いは、小学校からの親友。
ですが、ある時期から次第にその親友がきつい言葉を私に言うようになってきたのです。
彼女の機嫌を損ねてはいけないー。
元々、小学校の頃からどこか、“怒らせてはいけない”“反抗してはいけない”
という思いを持っていた私。
「嫌われたら、自分の居場所がなくなってしまう」――それが私の不安のすべてでした。
クラス替えがなかった小学校時代は、もし親友と関係がこじれてしまえば、その後何年もつらい思いをするかもしれない、と勝手に想像していたのです。
そんな関係性だったからこそ、彼女が私にきつい言葉を投げかけても、傷つきながらも笑って受け流すことしかできなかったのです。
けれど、その言葉は次第にエスカレートしていきました。
毎日のように言われる心ない一言が、心にナイフのように突き刺さり、私はついに笑うことすらできなくなっていったのです。
「どうしてあんなことを言うのだろう」と相手を理解しようとする苦しみ
それでも、私は親友のそばにいたかった。
なぜそんな言葉を言うのか、どうして私を傷つけるのか――私はひとりになると必死で理由を考えていました。
家庭環境なども色々考えてみたりして、
「親に反抗できないから私に発散をしているのかもしれない」
「家で彼女を怒る人がいなかったから、気ままになったのかも…」
そんなふうに考えて、私は彼女の気持ちを理解しようとしていたのです。
そして、どこかで「仕方ないよね」と許すことで、関係を保とうとしていました。
けれど、心は限界を迎えていました。
精神的に追い詰められていた私は、「母に相談しようか」と思ったものの、こんな不安がよぎって止めてしまったのです。
「心配をかけてはいけない」
「大ごとになったら、学校で自分の居場所がなくなるかもしれない」
そんな思いが頭の中をぐるぐると巡り、結局誰にも言えず、私の中だけでその苦しみを抱え続けていました。
愛犬の存在と、はじめて書いた“反抗”の言葉
親友との登下校時、親友の機嫌がいいかどうかで毎日が左右され、そのきつい言葉に傷つきながらも私は毎日学校に通い続けていました。
ですがある日の夕方、一人で部屋にいる時に
「もう生きることに疲れた。楽になりたい…」
心の限界を迎え、絶望の淵に立たされてひとり声を殺して泣いていると、飼っていた愛犬のメリーが驚いた様子で尻尾を垂らしながら飛んできて、私の顔を一生懸命舐めてくれたのです。
まるでメリーが
「何かあったの?私はまゆちゃんの味方だよ!」
と慰めてくれている気がして、私は我慢していたすべての感情をようやく出せたのです。
しばらくして冷静になってから、“何で悪いことをしていない私が苦しまないといけないの?”と怒りが湧いてきて
どうせなら、もう言われないためにも、気持ちをぶつけたいと考えました。
そこで勇気を振り絞って、当時親友と続けていた交換日記に、本当は嫌だったと“本音”を書きました。
それは、私にとって初めての“静かな反抗”でした。
相手の気持ちばかり考えて動けなかった私が、自分を守るために動いた瞬間だったのです。
その後、親友からノートを渡されたとき、少し怒っているようにも見えましたが、何も言われませんでした。
ただ、そのノートには黒くぐちゃぐちゃに殴り書きがされていて――それを見たとき、怖さはありました。
けれど、その出来事を境に、彼女のきつい言葉は次第に減っていき、少しずつ関係性は改善されていきました。
そして同時に、この経験がきっかけで、私は「親友がいないとダメな自分」から少しずつ自立ができるようになりました。
やがて進学で別の学校に通うようになってからは、本当の意味で「対等な関係」として親友になれたのです。
この頃の苦しかった出来事から、私は「なぜ人は生きているのだろう?」という漠然とした問いを抱き続けるようになりました。
そしてそれは、のちに私が「心」や「生き方」について深く学ぶ道につながっていくことになるのです。
▲ 目次に戻る
結婚・育児編:頑張っても報われなかった日々
そんな痛みや孤独を抱えた私でしたが、なんとか学生生活を乗り越えて高校を卒業。
その後就職し、職場で出会った夫と結婚。
子どもにも恵まれ、「これから幸せな家庭を築いていけるんだ」と未来に希望を抱いていました。
ですが、実際の生活は想像以上に孤独なものでした。
理想の妻・母になろうとしていた私
夫は仕事が忙しく、家事や育児はすべて私ひとり。
周囲に頼れる人もおらず、「いいお母さんでいなきゃ」「ちゃんとやらなきゃ」と自分を追い込んでいきました。
友人と会話をしても、立場の違いを感じるばかり。
感情を吐き出す場もなく、「私の気持ちは誰にも分かってもらえない」という寂しさがどんどん大きくなっていったのです。
感情を抑え続けた私と、夫とのすれ違い
最初のうちは「私がやるべきこと」と思って家事や育児を頑張っていましたが、徐々に心の余裕がなくなっていきました。
夫が手伝おうとしない姿に対して不満が募り、でも「言ったら嫌われるかも」と言えずに我慢。
その我慢が限界を超えたとき、私は感情を爆発させてしまいました。
「いつも私ばっかり家のことしてるんだから、たまには手伝ってよ!!」
でも、私が泣いて訴えても、夫は何も言わず、ただ黙り込むだけ。
言い返すでもなく、受け止めるでもなく、反応のないその姿に、私はますます傷ついていきました。
『こんなに苦しいのに、どうして分かってくれないの?』
何度も同じことを繰り返すうちに、私は次第に疑問を抱くようになりました。
「なぜ、仲良くしたいと思っているはずなのに、その度にケンカになってしまうのだろう…」
まだその頃は、自分の本当の気持ちを上手く伝えられていないことにも気づけていませんでした。
心の転機〜自己理解がはじまった瞬間|「鏡の法則」との出会い
そんなある日、ふとしたきっかけで手にとったのが「鏡の法則」という一冊の本でした。
その時はまだ、「深刻な悩み」までは感じていなかったけれど、心の奥にずっと小さなモヤモヤを抱えていたのだと思います。
後から振り返れば、この出会いが私にとって大きな転機となりました。
その中には、「人生は自分の心を映し出す“鏡”である」という考え方が書かれていました。
これまでの私は、「夫がわかってくれない」「なんで私ばかりが我慢しなきゃいけないの?」と、外側の状況に対して不満を抱き続けていました。
でもこの本を読んだとき、私はハッとしたのです。
なぜなら、夫を責めていたことが、じつは子どもの頃に父に対して感じていた寂しさや怒りだったのだと気づいたから。
この気づきは、それまで私が心のどこかで探し続けていた「真実」に出会えた。
そんな大きな心の変化を感じた出来事でした。
そして私は、「もっと自分の内側を知りたい」「自分と向き合いたい」と強く思うようになりました。
この出来事が、私にとって“自己理解”への第一歩”となったのです。
管理職チャレンジ編:自己否定から自己受容へ
二人目を出産してしばらく経った頃、友人の紹介で営業の仕事を始めました。
人見知りで話すことが苦手だった私は、お客様の話を共感しながら聞くことで喜んでもらえることが増え、次第に「人の話を聞くことが自分の天職なのかもしれない」と感じるようになっていきました。
家庭と仕事の両立に疲れ果てた日々
やりがいも感じていたその仕事で、あるとき上司から「マネージャーにならないか」と声をかけていただきました。
キャリアアップに挑戦したいという思いと、これまで支えてくださったお客様や仲間たちとの別れに迷いながらも、私は新たなステージに進む決断をしました。
ところが、マネージャーとしての責任感やプレッシャーは想像以上に大きく、私はだんだん自分の方向性を見失っていきました。
「いいマネージャーでいなきゃ」「できる人と思われなきゃ」と、つねに理想の自分を演じようとし、誰にも頼れないまま仕事を抱え込む日々。
そして、毎日帰宅が遅くなり、家のことが疎かになり、子どもたちにイライラをぶつけてしまうことも増えていきました。
そんな自分に嫌気がさし、「私、母親としてもダメだな…」と、どんどん自己否定の気持ちが強まっていったのです。
家族の言葉が私の心を救ってくれた
そんなある日、異動してきた上司との関係性で悩むことが重なり、心も体も限界を迎えました。
頭痛・吐き気・睡眠障害など、身体にもはっきりと症状が現れはじめ、私は初めて家族に弱音を吐きました。
「仕事、辞めようかな…」
それまでどんなことも「頑張らなきゃ」と耐えていた私が口にした本音でした。
すると、中学生だった娘が、優しく明るい口調でこう言ったのです。
「いいやん、辞めなよ」
そして夫も、「まゆちゃんが辞めたいなら、辞めたらいいと思うよ」と言ってくれました。
そのとき、私の中で何かがほどけるような感覚がありました。
「頑張らなくても、できなくても、私という存在を受け入れてくれる人がいる」
そう思えたことが、涙が止まらないほど嬉しかったのです。
そのとき私は、はじめて“無理に頑張らなくてもいいんだ”という安心感と、自己受容の感覚に触れたような気がしました。
「もっと自分を知りたい気持ち」が私を動かした
この出来事をきっかけに、私は本格的に自分の内面に意識を向けたり、学びを深めるようになりました。
それは、誰かを助けたいというよりも、まずは自分自身を理解したい、もっと自分のことを知りたいという思いからでした。
以前から「なぜ人は生きるのだろう」と考えていた私にとって、
内面と向き合うことは、“生きる意味”を探す旅のようでもありました。
そこで出会った考え方や学びの中に、私は確かな希望と可能性を感じたのです。
自己理解が深まるにつれて、これまで抱えてきた自己否定や罪悪感に対しても、「そう思ってしまう自分がいてもいい」と自己受容がさらに深まりました。
そして私は、日本アドラー心理学振興会認定心理カウンセラーの資格を取得し、
さらに人間行動学に基づいた学びを深め、トレインド・ディマティーニ・メソッド・ファシリテーターの資格も取得。
こうした学びを重ねる中で、同じように「こんな自分じゃダメ」と思いながら苦しんでいる方々の力になりたい。
そう強く感じるようになり、カウンセラーとしての活動を本格的に始めることを決意したのです。
まとめ|自己否定はいつからでも手放せる
幼少期からまわりの人の気持ちばかりを気にして頑張り続け、
「こんな自分じゃダメ」と自分を責めてきた私。
でも、少しずつ自分と向き合い、「そのままでもいい」と思えるようになったことで、心がラクになっていきました。
自己否定は、がんばって直すものではなく、気づいたときから少しずつ手放していけるもの。
あなたも、今日から“自分を理解する一歩”を踏み出してみませんか。
公式LINEのお知らせ
プロフィール記事を読んでくださったあなたへ。
悩みを一人で抱え込んでいませんか?
今回、公式LINEにご登録いただいた方に特典をご用意しました。
- イライラ、モヤモヤを言語化して自分を知るための「自己理解ワーク」
- 【期間限定】30分の無料相談
「どうしたらいいか分からない…」
「まずは話を聞いてもらいたい」
小さな一歩が、自己理解と自己受容の大きなきっかけになりますように。